第24話 意外なプレゼンター
姉妹エッセイ“有限要素法よもやま話”第22話(4元数をもう一度)で登場してもらっているケイリーと同時代を生きたイギリスの数学者に、シルベスター(Sylvester;英1814-1897)という人がいます。
工学関係の書籍ではほとんど顔を出さない(機構学分野での登場があるようですが)人物ですが、行列論(シルベスターの慣性則というのを行列の参考書で見かけます)ほか結構多くの数学分野で貢献した人で、第一級の数学者でありました。シルベスターはケイリー同様、弁護士をしていた時代があり、その関係でケイリーと知り合いになり、彼から不変式論という新しい数学を教えてもらうと、それを引き継いだ形でその分野に貢献した人のようです。
不変式論というのは、例えば2変数2次式のような多項式に変数の1次変換を施した時、多項式の定係数だけでできる、不変なる量を研究する数学分野です。不変式論は19世紀後半の一時期、注目された数学であったようです。アインシュタインの相対性理論も、これがなかったら発見されなかったといわれているようです。
![]()
ケイリーとシルベスターは、生涯の親友同士で双子の兄弟のようにして不変式の理論には貢献したそうです。双子の兄弟といっても、両者の性格、人生行路は全く対照的でありました。比較的穏やかな人生であったケイリーに比べると、シルベスターの方は起伏の激しい波乱の一生でした。
われわれが見ることのできる肖像写真での風貌は、両者の性格を全く反対に入れ替えたのではと思いたくもなります。落ち着き払ったシルベスターの風貌からは、そのどこに単純ではない彼の性格が宿んでいるのかと思いますが、後世の人間から見ると、面白い生涯を送ったのはシルベスターの方です。
ケイリーは小説の主人公にはなり得ませんが、シルベスターは詩人でもあり、文学、音楽にも造詣が深く、ちょっとした大河ドラマの主人公でありました。ただ、彼には学生時代から宗教面で周りと対立することが多々あり、損な人生を強いられていたのも事実です。
シルベスターで特筆すべきことは、一般には若年の活躍で終わってしまう数学の世界にあって、60歳という高齢を過ぎてなお数学者の輝きを失わなかったことです。新大陸で開設されたジョンズ・ホプキンス大学の数学者として招かれたのがなんと63歳のときだったそうです。それからでも意気軒昂な数学生活を送ったということですから拍手喝采ものですね。
そのシルベスターが数学者としては不遇時代、数学を離れて保険会社の統計会計士をしていたことがあります。そのとき、アルバイトで数学の個人教授をしていました。しかも、この当時としては珍しい女性に対してです。その女性とはなんと後のクリミアの天使ナイチンゲール(Nightingale;英1820-1910)だったのです。
実際、ナイチンゲールが数学者(統計学者)であったとは、ちょっとした“トリビアの泉”ですね。

後年、彼女が保健衛生に熱中する時期、頑固な軍部官僚を説得するのに数字を統計処理して分かりやすいグラフにして持っていったといいます。そのグラフもかなり独創的であったようです。現在のような表計算ソフトなど何もない時代になかなかのプレゼンターでした。
ナイチンゲールがちょっとした数学者であったということも意外な面ですが、彼女にはいまひとつ意外な事実があります。ナイチンゲールの名を不朽のものにしたクリミア戦争での看病中に熱病にかかってしまい、その後の彼女の人生はほとんど病人生活を強いられていたということです。白衣の天使であったのもクリミア戦争当時の2年間だけだったそうです。それでも、90歳まで生き抜いた女性でありました。
2004年2月記
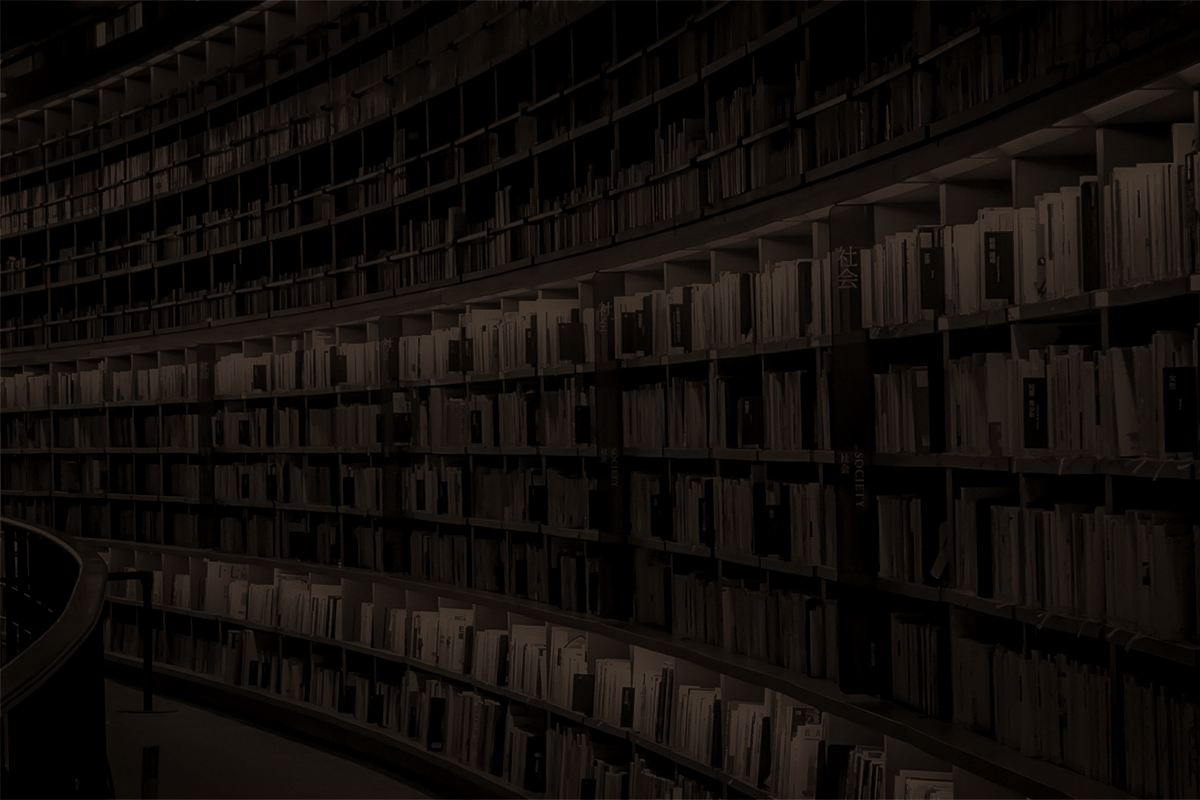

読者からの寄せられたコメント
[…] 「ジョージ・ブールは、ケンブリッジの数学の新しい動きとは全く無関係だった。しかし、彼は仏語がよくできたので、ラクロアの微積分学、ラグランジュの解析力学(ラグランジュによる『解析力学』はラプラスの『天体力学』と共に18世紀末の古典的名著とされる(ジョゼフ=ルイ・ラグランジュ – Wikipedia))、ラプラスの天体力学、ヤコビ、ポアソン等を独力で読んだ」「ジョージがどうしてこのような古典を読むことができたか?それは、彼が献身的に奉仕していた社会事業メカニック・インスティテュート(日本語で言うとしたら、科学的技術思想普及協会)があったから。これは設置者は英国政府であるが、運営は自治体と市民のボランティアにまかされていた。ブールの父は、これに熱心に奉仕しており、望遠鏡、顕微鏡、カメラ・オプスキュラ等をジョージに手伝わせてつくり、市民達に見せて啓蒙に努めた。父の商売がうまくいかなくなったのもこの趣味に熱心すぎたことも理由の一つである。ジョージも1834年には田舎から帰り、ボランティアとして熱心にこの協会のために力を尽くした。彼が19歳のとき、はじめてこの協会でアイザック・ニュートンについての講演を行った。彼は19歳のとき、父のあとを継いで評議員となり、権利を得ていたので、この協会に附属する図書館でフランスの数学の古典を読むことができた」「ジョージ・ブールはラグランジュの「Calcul des Fonctions(関数の計算)」を読み、大きく影響された。最初はニュートンにならって、応用数学、特に天体力学をやるつもりだったのだろう。しかし、フランス語の文献を次々に読むうちに純粋数学にひかれていったに違いない。ジョージ・ブールは、大学には行かなかったが、リンカンの近くにケンブリッジ大学卒業の数学者Sir Edward ffrench Bromheadがおり、メカニック・インスティチュートの会長であり、Analytical Societyの一員でバベッジととても親しかった。ブールの仕事にはこの人の考え方が大きく影響している。時期は1838-1840頃。ブールは自分の考えを彼に聞いてもらっており、多くの手紙の往復がある。1839年,ジョージが24歳のとき、ケンブリッジ・ジャーナルに掲載された論文は「Research on the theory of Analytical Transformations, with a special Application to the reduction of the general Equation of the Second order.」という論文(ラグランジュの解析力学に刺激されて発見したもの)である。ただ、この論文を掲載できたのはCambridge Mathematical Journalの編集者Duncan F. Gregoryの親切な指導が大きかった。彼はライプニッツの記法を勇ましく取り入れた第一人者。ジョージは数学論文を書いたのははじめてだったので、書き方も普通ではなかったので、グレゴリーは直ちに受理したわけではなく、丁寧に書き方を直してやって受理したのがこの論文である。次に特筆すべき論文は「A General Theory of Linear transformation」(1841.11)(Cambridge Mathematical Journal)。これが不変式論のはじまり。これ以後、不変式ろいうテーマについてもう一つ論文を書いたが、その後は彼は何もせず、ケイリーとシルベスターが活発な仕事を始めた(第24話 意外なプレゼンター | FEMINGWAY)(Introduction to Mathematical Logic)。これらの結果により、ブールは数学者仲間に知られるようになった。そして、1844年ロイヤル・ソサエティにはじめて論文を送った。しかし、これはジョージに学歴がないために受け取ることすら断られそうになったが、一人のアカデミアンによって受理された。この論文のタイトルは「General Method of Analysis」(1844)であり、グレゴリーの考えを発展させた線形微分方程式(高階)の記号解法である。ロイヤル・アカデミーは、これに対してゴールドメダルを贈り、ブールは有名になった」 […]